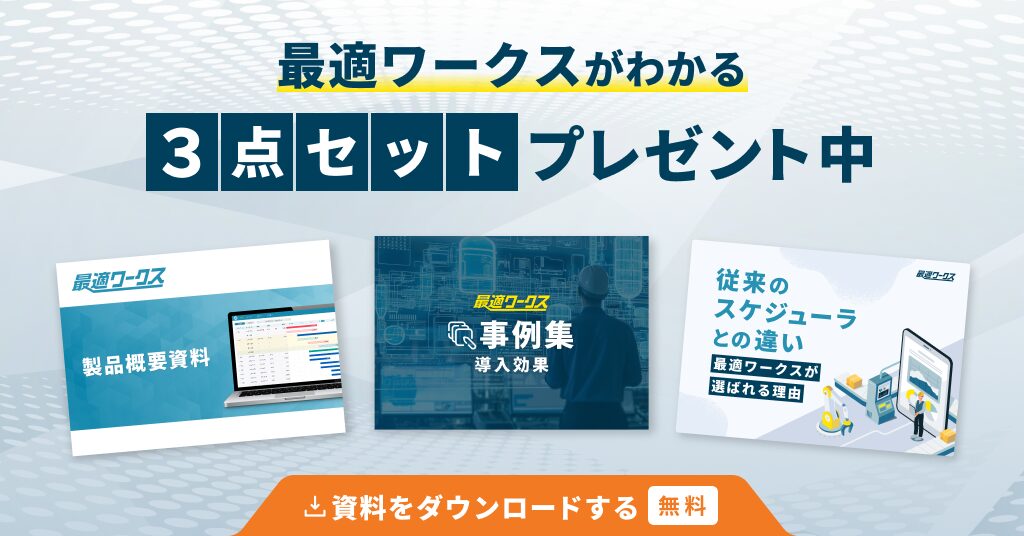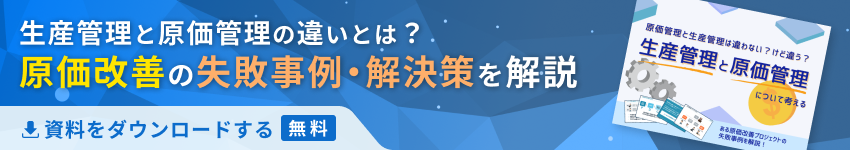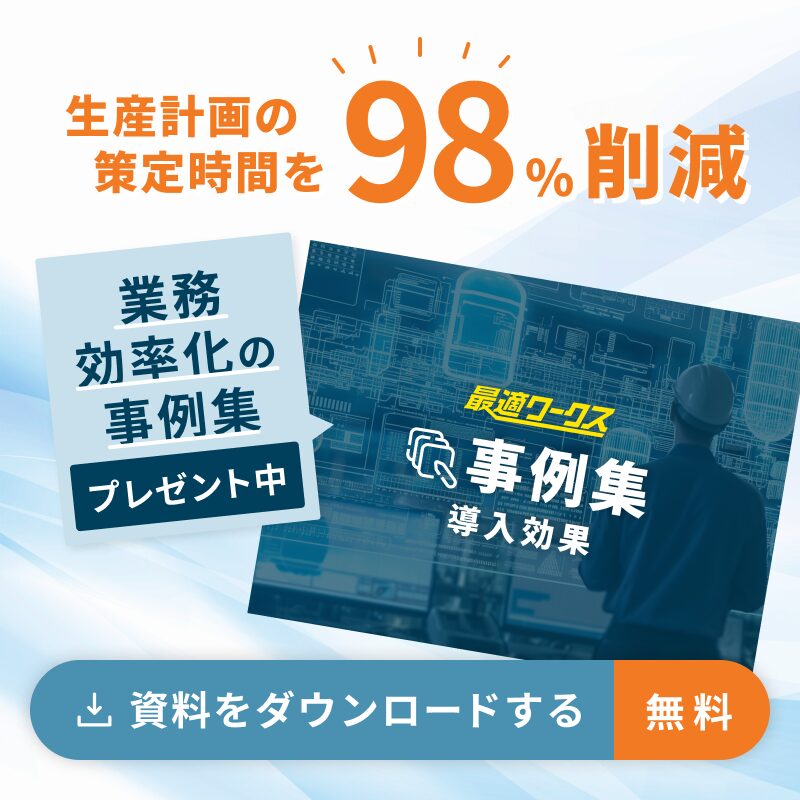- コラム
製造業におけるERPの導入メリットと選び方

ERPとは?製造業での役割と重要性
ERP(Enterprise Resource Planning)とは?
ERP(Enterprise Resource Planning)とは、企業の持つ様々な資源(ヒト、モノ、カネ、情報)を一元的に管理し、業務プロセス全体を最適化するためのシステムです。
会計、人事、生産管理、販売管理など、企業に点在するデータを統合し、その情報を元に企業の状況を正確かつタイムリーに把握し、経営戦略や戦術を決定していきます。企業全体の経営資源を有効活用し、競争力強化に繋げることが期待できます。
基幹システムとの違い
基幹システムは、対象の基幹業務ごとにそれぞれ独立したシステムを指し、異なる部署とデータをやりとりする際は、システム間の連携が必要です。
製造業では、従来より生産管理システムや販売管理システムなど、個別の基幹システムが導入されてきました。しかし、これらのシステムは業務ごとに最適化されているため、部門間の連携が弱く、情報が分断されがちでした。ERPは、従来の個別システムのデータを統合的に管理し、部門間の連携を強化することで、全体最適を図ります。
| ERP | 基幹システム | |
|---|---|---|
| 目的 | 企業全体のリソースを統合管理し、最適化すること。経営判断の迅速化を実現 | 特定の業務を支援し、個別最適を図る。生産管理・販売管理・会計など、各業務の効率化 |
| 対象 | 企業全体 | 特定の業務領域 |
| データ連携 | 統合データベースを活用し、リアルタイムで情報共有 | 独立したシステムなので、システム間連携が弱い |
なぜ製造業にERPが必要なのか?
現代の製造業は、多品種少量生産やグローバル化、顧客ニーズの多様化など、市場環境の急激な変化に直面しており、迅速な意思決定と柔軟な対応力が不可欠です。さらに、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、データに基づいた経営判断の重要性が増しています。
こうした課題を解決し、競争力を高めるために、ERPの導入による業務の統合管理が不可欠です。部門ごとに異なるシステムを使うと情報が分断され、データの不整合や手作業の増加を招きますが、ERPは生産・在庫・購買・販売・会計などの業務データを一元管理し、二重入力の削減や業務の標準化を可能にします。
その結果、リアルタイムな情報に基づく迅速な意思決定、在庫の最適化、原価管理の精度向上などが実現し、企業の全体最適化と競争力強化に大きく貢献します。
ERPの主な製造業向け機能
ERPには、業務プロセスに対応した様々な機能が存在します。現在は、業種に応じたERPパッケージなども開発されており、製造業向けERPでは、主に「受注・販売管理」「在庫・購買管理」「生産管理」「財務・会計管理」などの機能が求められます。
受注・販売管理
顧客からの受注、納期管理、取引先情報の一元管理を行います。受注から出荷までのプロセスをスムーズにし、リードタイムの短縮、コスト削減、そして取引先との良好な関係構築を支援します。
在庫・購買管理
購買管理機能は、製品の製造に際し、必要な部品・資源の調達にかかわる一連のプロセスを管理する機能です。原材料、仕掛品、完成品の在庫状況を正確に把握し、サプライヤーへの発注から入荷までのプロセスをスムーズにし、発注不足や発注過多を防ぎます。適切な在庫量を維持することで、在庫コストの削減と顧客満足度の向上に貢献します。ロット管理やトレーサビリティ機能も重要です。
生産管理
生産管理とは、製品の製造に際し、生産計画を立てることや、製品の生産工程を管理することを指します。生産管理機能では、需要予測システムやBIツールと連携し、生産計画の立案、製造現場における進捗状況のリアルタイムな把握を支援します。資源の最適配分、ボトルネックの解消、納期遅延の防止に貢献し、生産効率の最大化を目指します。
会計管理
会計管理機能は、企業の売上やコスト・利益等の情報を収集し、財務状況の正確な把握を実現します。製造業においては、製造コストの分析、製品別・部門別の利益管理、そして経営状況の把握を可能にします。正確な原価計算に基づいた適切な価格設定、無駄なコストの削減、そして収益性の向上に貢献します。
人事・労務管理
人事・労務管理機能は、従業員の勤怠管理、シフト管理、給与計算、人事評価などを効率的に行います。労働時間の適正管理、人件費の最適化、そして従業員の満足度向上に貢献します。製造業特有の複雑なシフト管理に対応できる機能が重要です。
ERP導入のメリットとデメリット
ERPの導入は、様々なメリットをもたらしますが、同時に注意すべき点も存在します。
メリット
データの一元管理による業務効率化
ERPを導入することで、受発注・生産管理・在庫管理・会計などの業務が統合され、部門ごとに分散していたデータの一元管理が可能になります。これにより、手作業や二重入力の削減、業務プロセスの標準化が進みます。
経営判断のスピードアップ
製造現場の生産進捗や在庫状況、販売データなどがリアルタイムで可視化され、経営陣による迅速な意思決定が可能になります。特に、需給調整やトラブル対応のスピードが向上することで、市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応し、競争優位性を確立することができます。
在庫の適正化とコスト削減
過剰在庫や欠品を防ぐための在庫管理が精度向上し、適正在庫の維持が可能になります。これにより、倉庫コストや材料費の削減につながります。また、在庫や物流を管理することによって、リードタイムの短縮が見込めます。
デメリットと解決策
高額な導入費用
ERPの導入には、システムのライセンス費用、カスタマイズ費用、時には、ハードウェアの整備、導入コンサルティング費用など、多額の費用がかかることがあります。特に、中小製造業にとっては負担が大きい場合があります。
解決策:クラウドERPの活用を検討しましょう。クラウドERPは、初期費用を抑えられ、スモールスタートが可能です。
既存業務とのギャップ
ERPの標準機能が、既存の業務プロセスに合わない場合があります。
解決策:ERP導入前に、業務プロセスを整理し、ERPの機能とのギャップを明確に把握することが重要です。場合によっては、ERPに合わせて業務フローを変更する必要があり、従来のやり方に慣れている現場の抵抗感が生じることがあります。業務改革が求められるため、現場の理解と協力が不可欠です。
カスタマイズの追加コストが膨大
標準機能だけでは自社の業務にフィットしない場合、カスタマイズやアドオン開発が検討されます。しかし、システムが複雑化し、運用負荷が増加する可能性があります。また、カスタマイズには追加費用が発生します。
解決策:導入目的を明確にし、必要な機能を見極めたうえで、自社の業務に適したシステムを選定することで、無理なカスタマイズを避けましょう。 また、ERPのカスタマイズを最小限に抑えるためには、標準機能を活用しつつ、外部ツールの併用や段階的な導入を検討することが重要です。
ERPの種類と選び方
ERP導入を成功させるためには、自社のビジネスモデルや規模、そして将来的な成長戦略に最適なERPを選択することが不可欠です。ERPには様々な種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。
クラウドERP vs オンプレミスERP
| クラウドERP | オンプレミスERP | |
|---|---|---|
| 特徴 | ベンダーが提供するクラウド上にシステムを構築し、インターネット経由で利用する形態 | 自社のサーバーにシステムを構築し、自社で運用・管理する形態 |
| メリット | ・初期費用を抑えられ、導入期間が短い ・柔軟な拡張性があり、アップデートもベンダーが行うため運用負荷が低い ・どこからでもアクセス可能 |
・高いカスタマイズ性があり、独自の業務プロセスに合わせたシステム構築が可能 ・セキュリティ面での自由度が高い |
| デメリット | ・特定の業務に特化した深いカスタマイズは難しい場合もある ・セキュリティ面でベンダーに依存する部分がある ・継続的な利用料が発生する |
・初期費用が高額 ・導入期間が長い ・運用・管理に専門知識と人員が必要 ・拡張性が低い |
ERPの種類と比較
フルスクラッチ型ERP(完全カスタマイズ)
- 特徴:既存のパッケージを使用せず、自社の業務に合わせて完全にゼロからシステムを開発する形態。
- メリット:独自の業務プロセスに完全に適合したシステムを構築できる。他社との差別化を図ることができる。
- デメリット:開発費用が非常に高額。開発期間が非常に長い。開発・運用に高度な専門知識と人員が必要。
統合型ERP(オールインワンパッケージ)
- 特徴:企業の主要な業務機能を網羅したパッケージ製品。導入・運用が比較的容易。
- メリット: 幅広い業務に対応できる。導入期間が比較的短い。比較的安価に導入できる。
- デメリット: 企業の特定の業務プロセスに合わない場合があり、業務をシステムに合わせる必要がある。不要な機能が含まれている場合がある。比較的カスタマイズの自由度が低い。
コンポーネント型ERP(必要機能だけ導入)
- 特徴:ある程度の業務単位(会計、販売、生産、総務、現場など)で導入し、後から機能を追加・拡張できる。
- メリット:初期費用を抑えられる。必要な機能だけを選択して導入できるため、無駄がない。拡張性が高い。
- デメリット:各コンポーネント間の連携に注意が必要。ベンダー選定が重要。
自社の規模、予算、業務の複雑さ、そして将来的な成長戦略などを考慮し、最適なERPを選択することが重要です。導入前に十分な検討を行い、複数のベンダーから見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
ERPの導入ポイント
ERPの導入を成功させるためには、事前の準備、適切な導入手順、そして既存システムとの連携が不可欠です。
ERP導入前に準備すべきこと:現状の可視化
システム選定前に、まず自社の現状業務を可視化することが最も重要です。各部門の業務プロセス、現在使用しているシステム、課題などを洗い出し、ドキュメント化します。
このプロセスを通じて、ERPに求める要件を明確にし、導入目的を共有することで、プロジェクトの成功率を高めることができます。業務フロー図の作成、課題の明確化、そして優先順位付けを行いましょう。
成功するERP導入の流れ
ERPの導入は、以下のステップで進めることが一般的です。各ステップにおいて、関係各部署との連携を密に行い、進捗状況を共有することが重要です。
- 要件定義:現状業務の可視化に基づき、ERPに求める機能や性能、導入目的などを明確に定義します。
- ベンダー選定:要件定義に基づき、複数のERPベンダーから提案を受け、比較検討します。自社の規模や業務内容に最適なベンダーを選定しましょう。
- テスト運用:本稼働前に、選定したERPシステムをテスト環境で実際に運用し、問題点や改善点を洗い出します。
- 本稼働:テスト運用で確認された問題点を修正し、本番環境でERPシステムを稼働させます。
製造業でよくある「ERPだけでは解決できない課題」
生産スケジューラとの併用が鍵
ERPは在庫管理や受発注、生産管理・計画の基盤を担いますが、需要変動への即時対応や詳細なスケジューリングの最適化は苦手です。例えば、急な受注変更や設備トラブルが発生した際、ERPだけでは最適な生産スケジュールを即座に組み直せず、手作業での調整が必要になります。
そこで有効なのが、生産スケジューラとの併用です。生産スケジューラは、現場の稼働状況や生産能力を考慮し、最適な生産順序を瞬時に計算。これにより、変動に柔軟に対応し、リードタイム短縮や生産効率向上を実現できます。
まとめ:ERP導入を成功させるために
ERP導入成功の第一歩は、自社の業務に合ったERPを選定することです。規模、業務内容、将来戦略を考慮し、クラウド、オンプレミス、フルスクラッチなど、最適なタイプを見極めましょう。導入前には、現状業務の可視化、導入目的の明確化、要件定義とベンダーとの密な連携が、ミスマッチを防ぎます。
大規模な導入はリスクを伴います。スモールスタートで部分的に導入し、効果を検証しながら段階的に拡大することも検討しましょう。
変化の激しい製造業において、ERPは競争力を維持・強化するための重要な鍵となります。データの一元管理により、迅速な意思決定、業務の最適化、そして新たなビジネスモデルの創出を可能にするDX推進の基盤になります。ERPを積極的に活用し、競争力を高め、持続的な成長を目指しましょう。
ERPでは見えない現場のムダ、生産計画DXの「最適ワークス」で見える化。
生産管理の起点となるのが「生産計画」です。DX(デジタルトランスフォーメーション)を始めるなら、まずはこの生産計画から取り組むことをおすすめします。
「生産スケジューラの導入費用をもっと抑えたい」「できるだけ早く導入したい」「導入後にきちんと使いこなせるか不安」といったお悩みをお持ちの方には、「最適ワークス」の導入をぜひご検討ください。最適ワークスの魅力は、コストパフォーマンスの高さ、迅速な導入、使いやすいシンプルな画面UI、そして充実したサポート体制にあります。月額15万円という手頃な価格で、AIによる高度な最適化ソリューションをご利用いただけるのは、大きなメリットです。
また、クラウドサービス(SaaS)で提供されているため、初期のハードウェア投資や複雑なシステム構築は不要です。そのため、導入スピードも非常に速く、時間とリソースを節約しながら、迅速に業務改善を始められます。シンプルで直感的な画面UIにより、特別なIT知識がなくても誰でも簡単に操作できます。また、カスタマーサクセスチームが導入後もユーザーに寄り添いながら支援し、最適ワークスを最大限に活用していただけるようサポートします。低コストでありながら高機能、そしてサポートも充実している最適ワークスは、DXや業務改善の第一歩として最適なサービスです。。